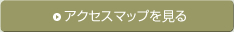2024年11月9~10日に九州教育学会が開催されました
2024年11月9日、10日に第76回九州教育学会が熊本学園大学を会場にして行われました。

本研究室からは、以下の2名が個人発表を行いました。
・餅井 京子(九州大学大学院・学術協力研究員)「学校事務におけるカリキュラム・マネジメント~多様な職種の協働で創る教育課程~」
・小椎葉 大樹(九州大学大学院)「現代教員養成の『開放制』原則に関する一考察 ―行政と大学外機関の協働を通して―」
学会当日は、九州各地から多くの研究者・教育関係者が参加し、活発な議論が行われました。
本研究室の発表に対しても、発表内容や視点に関して多くの質問・コメントをいただき、今後の研究の方向性を考える上で大きな刺激となりました。


以下、発表者からいただいたコメントになります。
餅井:
本研究は、田村(2022)の開発したカリキュラムマネジメントモデルに則り、学校事務職員がカリキュラムマネジメントに参画することで、このモデルの教育条件整備の要素における課題を明らかにすることを目的としています。
田村(2022)の開発したカリキュラムマネジメントモデルは、実践の指標となるモデルとして学校現場で多く用いられているところです。しかし、学校事務職員の視点から開発されたモデルは未だ開発されていません。そこで、教育条件整備の側面を重要視する田村モデルを使用することで、表現されていない教育条件整備の側面や、より違う方法で表現されるべき教育条件整備の要素を実践を行う中で明らかにし、このモデルを違う角度から展開することの必要性を述べました。
会場の会員から多くの質疑、御意見を頂きました。その中に「学校事務職員がカリキュラムマネジメントに参画するためのハードルは何か?」という質問がありました。この研究の「問い」の一つとなる核心を突いた御質問であり、カリキュラムマネジメントの目的に改めて気づかされました。教育の専門性確保のため、今後、教育内容・教育活動系列と教育条件整備系列の並走はより重要になってくると考えられます。学校経営における教育条件整備の側面に関する研究、特に、教員による条件整備ではなく、学校事務職員による条件整備の展開は、今後より研究が深められる必要があると考えています。会場でいただいた示唆をもとに、今後、研究を深めていきたいと思います。
今回の自由研究発表にあたり、直前まで御指導をいただいた元兼先生、前日まで助言をいただいた研究室の皆様、会場で御意見・御質問をいただいた皆様に心から感謝申し上げます。
小椎葉:
今回の学会発表は、私にとって初めての個人発表でした。本発表では、新しく生起している教員養成の取り組みを事例として、これまでの開放制議論を再検討する論考を紹介しました。発表を通して、自身の研究の面白さや新しさを他者に伝えることの難しさを痛感すると同時に、参加者の方々からの質問を通して、自分の論考の未熟さが浮き彫りになったような内容だったと感じています。
一方で、ゼミでは得られない新たな視点や意見をいただけたことが非常に新鮮で、自身の研究を多くの方に議論してもらえる楽しさも実感する機会となりました。今回の発表で得られた知見や指摘を踏まえて、今後の研究活動にさらに力を入れていきたいと思います。
本学会で得た経験を糧に、研究室一同、今後も研究活動をより一層深めてまいります。
(文責:小椎葉大樹)